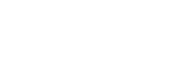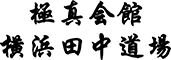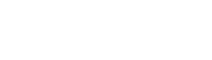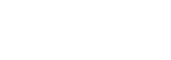志というものは、春の雪の様に儚く溶けて消えやすい。
人として生涯の苦労は、その志の高さをいかに守り抜くかによる。
でも、その高さを守る工夫は特別なものではない。
日常生活の自らの規範・規律にあるのだろうと思う。
たとえば、しゃべり方、動作、人との付き合い方、呼吸の仕方、お酒の飲み方遊び方
それら全てが志を高く保つためという思いに通じていなければならないと思う。
つまり、一旦、志を立てたらその成就に精根使い果たし、卑しくも弱音など吐いてはいけないのだ。
たとえば川が堤を切って氾濫する時のように、その情熱は止め処なく広がらねばならない。
理由も意味もなく、まるで自然現象のごとく、水の勢いのまま行きつくところまで行く。
若さと、情熱と、志とは、そういうものではないだろうか。
春は、いつの間にか桜とともにやってきていた。
ふと見ると庭の木香バラに若葉が目立ってきた。
あと一か月もすれば庭一面が木香バラの黄色一色に色づくはずだ。
しかし、その花も長くはもたず呆気なく花は散り、庭の活気は消えうせてしまう。
それはまるで人の臨終に立ち会うようなものかもしれない。
人は、ぼろに身を包み、こちこちの板の上に身を横たえ、苦しみ悶えながら息を引き取るようなもの。
人はその板の上で手を合わせ、死に怯え、その間際まで神の助けをつぶやき続けるもの。
そして、いまわの時を迎え、怯えも消え、意識がすっと消えていくのだ。
生を受けた者は必ずそれを経験することになる。
人は花が散るように息を引き取って灰になる。
今の今まで、苦しんで、怯えていた、その人が旅立つその場に付き添うと人の命の重みが分かる。
心臓がぐっと押し上げられるような、息を呑むのもおこがましくなるような静寂の中で私は祈っていた。
すでに旅立っていった人々のことを思い、手を合わせ、しみじみ祈りたくなったのである。
その一人一人の顔を思い浮かべ、どれほどの恐怖に立ち向かって行ったことかと怖くなった。
忘れもしない。 私は亡き父の身になって、そして亡き義母の身になって、そら恐ろしくなっていた。
そして私は亡き父の為、そして亡き義母の為、祈っていた。
放蕩者として無駄な時間を過ごしていたことを悔やみ、うら寂しい、うら悲しいため息が洩れた。
父は「志」を全うできただろうか?
義母は「志」を必要とする孫に意を伝えきれただろうか?
多くの子供達、そして多くの青春を謳歌する若者達には、この儚く消えやすい「志」が必要なのだ。
私は、将来のある子供たち一人一人に真正面から向き合っている訳はそこにある。
今日一日、しっかり生きただろうかと私は毎日、自問自答しているのは、ただそんな訳からなのだ。