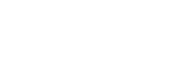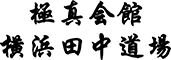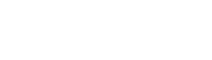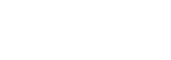答えのない問題
あなたは過去を許せますか? あなたは、もう自分の過去を許してあげたのですか? 人は自然に守られ、人に支えられて生きている。 人を蔑み、人を裏切り、そして人をあざけりながら生きている。 あなたは憎んでいた過去を忘れられますか? そして憎んでいた人の事を忘れられますか? あなたは何に背を向けて生きて行くのですか? 「人は、人によりて、人になる」 「子供は、大人によりて、良き社会人になる」 子供は感受性豊かに大人を観ている。 関心があるから観ている。 そして観ているその人の様な人生を送るようになる。 だから気を抜いてはいけない。 肩書や年収で人を判断する子供は、その親がそういう人だったのかも知れない。 一生懸命努力する子供は、きっとその親の後姿を観てきたのだろう。 でも悪口も、陰口も、重箱の隅を突っつく攻め口調も子供がやり始めた事ではない。 積乱雲と雷、雹や突風、そして地震とつなみ。 先の天候など誰にも分からない。 自然の中に人は生きている。 自然に守られ、また苦しめられながら生きている。 憎む人も、許す人も、大いなる宇宙の中に居る。 太陽は、いつもあなたを照らしている。 許すあなたも、憎むあなたも。 あなたは自分の過去を許せますか? 答えのある問題を解くのは大事な事。 しかし答えのない問題を心で反すうすることはもっと大事。
一粒、そして一秒
昨日、おとといがあって、今日の自分がある。 三か月、半年前の自分があって、今の自分がある。 3年、5年、10年、15年、そして20年、30年前の自分があって、今の自分がある。 1時間は3600秒。 1日は86,400秒。 1か月は約260万秒。 そして1年は約3110万秒。 30年では約9億3300万秒。 気の遠くなるような間、着実に砂時計は時を計っている。 だから、この1秒、1秒を無駄にしてはいけない。 人には固有の砂時計があって、一人一人の砂時計の大きさ、砂の量は生まれながらに差がある。 そして蝋燭が消えるように、その砂時計も最後の一粒が尽きたら、それでその人がその身体で生きる ことは出来なくなってしまう。 おもちゃの電池がなくなるように、砂時計の砂もいずれなくなってしまう。 だから、その一粒一粒、一秒、一秒を無駄にしてはならない。 私には無駄にしてはならないことがある。それは私が今まで味わった苦しみ、悲しみ、妬み、痛み。 それから何よりも人に与えて来てしまった苦しみ、悲しみ、妬み、痛みである。 若かりし頃、私は人の世話になるものかと思いながら生きて来た。 しかしもはや、その過去に立ち戻って、過ちを悔い改めることは出来ない。 今日、6月12日 二つの事件の判決が出た。 一つは、2014年3月に起きた柏の通り魔事件の判決。 「これでまた殺人ができる」という声が残った。 もう一つは、2014年9月に生活苦から実の娘を絞殺した判決。 「本当は私が死ぬはずだった。可純に申し訳ない」という声が残った。 失敗も、後悔も、そしてどんな嫌な事柄も、一つとして無駄なことはない。 人はその生涯の中でいったい何千人、何万人の人に出遭っていることだろう。 「もう、あの時には戻れない」 という過去をどれほど観て来たことだろう。 今日、私はいろんな経験をした。 そして明日の私はどんな経験をするのだろう。 今日、私はいろんな人に出遭った。 そして明日の私はどんな人に出遭うのだろう。 昨日の自分があって明日の自分がある。 今日の道端の蟻んこにも明日がある。 そして、田んぼに生まれる名もなきミジンコにも陽のあたる明日はきっとある。
幸せの基準
人は条件で幸せになれるほど、簡単な代物ではない。 お金があって、いい学校を出て、容姿はもちろん悪くない。 しかし、人間は、そんな条件だけで幸福な日々を送れる訳ではない。 でも、それが大事だと人は言う。 お金がないから喧嘩するんだ。と。 果たして本当にそうだろうか? お金があっても、卒業した学校が良くても、そして見た目がカッコ良くても あなたを大事に思ってくれている人かどうかは分からない。 人は誰しも幸せになりたいと願っている。 お金がある人もない人も。 そして自分の幸せだけを願っている。 親兄弟が自分をかけがえのない人だと思っているように 自分が嫌いなその人にも、その人をかけがえのない人だと思う親兄弟がいる。 その人を愛して、その人の幸せを願っている人たちがいる。 人の性格は千差万別。 顔も姿もおなじ人などこの世には存在しない。 71億分の一の存在だ。だからその存在自体が尊く愛おしい。 この71億人の人は、人と関わって生きてこそ、一人一人の幸福感は増す。 しかしそれも歳を取るに従い、人との関わりも減り孤独の中に生きるようになる。 まだ間に合う。幸せは逃げやしない。 いったいこれから世の中はどうなるのだろう。 自分はこのままでいいのだろうか? そんな時代だからこそ、今日一日を精一杯頑張った自分を労ってほしい。 よく頑張ったじゃないか。 失敗しても大したことじゃない。 いったい、何を欲張って生きているの?
奇跡の連鎖
今、私は生きている。 57年前のこと、荒川が氾濫して埼玉県川口市が水浸しになったらしい。 そんな話を母から聞いたことがある。 「ちょうどお前がお腹にいる時だったよ。」 「腰まで水に浸かりながら善光寺のお寺さんに避難したんだ。大変だったよ。」 母から勉強のことを教わったことはない。 自由に育ててくれた。 幼稚園の頃、私はいつも暗くなるまで池や畑で遊んでいるヤンチャ坊主だった。 今、自分は生きている。 産婦人科の病院は産まれたての赤子と母親だけのものではないと、ある雑誌に書いていた。 心が疼いた。 十月十日を前にして死産に直面した母親の記事だった。 産婦人科の病院はエコーの音を楽しみにしている母親達の場所。 急に慌てふためく医者と看護師に責任はない。 赤子がいなくても産後の入院生活を過ごさねばならない。 その母親は、やがて家に戻り灰色の日々を過ごすことになる。 涙は枯れ笑顔が消えた日が過ぎる。 心の傷はすぐには癒えるものではない。 時は過ぎ、季節が変わって、ようやく心は笑いで緩むようになる。 ほんの少しの時しか一緒にいられなかったその赤子もやはりその母親を選んで この世に来たのだろう。 今も昔も、人はみな奇跡の連鎖の中に生きている。 そんなことを思いながらその雑誌を閉じて、新聞に目をやった。 相変わらず下世話な記事が溢れていた。 三菱東京UFJの元エリート行員がお客の預金を横領して逮捕されたという。 元支店長代理はシニアファイナンシャルプランナーでもあった。 そして彼は横領したお金を自分の住宅ローンと遊興費に当てたらしい。 将来のライフプランに即した資金計画やアドバイスを行うファイナンシャルプランナーが 顧客の預金をだまし取る時代になってしまったのか。 これでは世も末ではないか? その男、52歳 川口市在住とある。 52年前、彼の母親は産婦人科の病院で奇跡の出会いに涙したに違いない。 幸福とは何だろう? 他人からは貧乏で不幸な人生だと思われても、その人が自分の人生を振り返った時 「あれこれといろんな浮き沈みが確かにあって苦労もした。そして些細な喜びしかない この人生でもまあこれでよしとしよう」と心底思ったとすれば、それは幸せな人生であった のではないだろうか。そして何よりも愛する人が幸せであってこそ、その思いは強くなる。 この52歳の容疑者も奇跡の連鎖の中に生きている。 そして彼の母親は今でも彼を愛しているのだろう。 幸せはいつもそこにあるのに、人はそれに気づいていない。
厄を落とす
今日という日は今日で終わり。明日は、また違う一日が始まる。 去年と同じような太陽が昇り去年と 同じような風が吹いている。 でも明らかに去年の今日と、只今、今日この日は違うものだ。 すべての物が刻々と変化している。 変化のない毎日のように見えて実は地球の軸が回転し 太陽の周りを移動する速度で変化を繰り返している。 そんな世界に我々は生きているということを 改めて認識したい。 その中で我々は空手の稽古を積んできている。 暑い日も寒い日も同じことを繰り返す。 刻々と変化する中で変わらない同じことを繰り返すことは 実は意外と難しい。 そのことにこだわる。そしてそのことを極める。そんな姿勢がなければ続くものではない。 人は生まれ、成長していく。 そして出会いがあって結婚し子を宿す。 子を産むと親として成長することを 求められ、やがて老いて土に還る。 その過程は多くの場合ほぼ同じである。但し、どのような姿勢で生きて どのような経験を積むかは人によって差がある。 楽しいことばかりの人生であって欲しい。 いい事だけが 起って欲しい。お金に苦労せず、病気もなく、事故もなく生きたい。 それが本音だ。 しかし、それが満額叶う確率は低い。 ならば苦労があって、涙して、汗して生きることになると腹を括らねばなるまい。 空手の稽古は楽ではない。 苦労の連続だ。伸びない筋を伸ばし、硬直する関節を無理やり 柔らかくしようとする。 そして何度も同じ動作を繰り返す。 決して楽しいものではない。 それが空手の稽古だ。 しかし私は空手の稽古は「厄落とし」だと捉えている。 楽しい事やいい事ばかりが起ると、その反動が必ず来た。 そして苦しい事が続くといつかきっと 生きて居て良かったと思う日に出会った。 その繰り返しを経験する中で私はこう思うようになった。 「ならば稽古の中で先に苦労をしておこう」と。 そう思って生きていると日常の中でいい事はそのまま起こり 辛い事は稽古で先取りした分、日常生活のそれは減ったように思えた。 つまり、人生、いい事と悪い事は同じ分しか起こらないようになっているのだ。
勇気の道
いつ何が起こるか分からない世の中になってしまった。 300年も前の鎖国の真ん中に生きた江戸の人は生まれて死ぬまでが安泰だったのだろう。 しかし今は、思うに任せない事ばかり湧いては弾ける世の中だ。 だから、そのたび毎に心がくじけてしまっていては身が持たない。 人は何度も転んで、何度も起き上がる事が出来る。 起き上がるごとに逞しくなってさえいたら、転ぶことも悪くはない。 ただ、転んで、すぐに立ち上がれない人も居る。 そんな心がくじけた人に向かって 闇雲に、こうすればいい、ああすればいいなどと安易な言葉を吐く無神経な人がいる。 相手の心を見ずに淡い夢を語るのは禁物だ。 フワフワした夢物語など何の役にも立たない事がある。 そもそも夢とは、いきなり叶うことはない。 子供の時に聴いたお伽話の世界でもない。 夢とは、今を必死に生きる、ぬかるみの世界の中にこそ、その種がある。 だから今を一所懸命、手抜きをせずに生きようと伝えて来た。 必死に生きることに意義と価値を見出し努力を続けるんだと伝えて来た。 そうする中で、夢に向かう道筋が眼前に現れてくる。 その道を一歩一歩、地面を確かめるように踏みしめて歩いていく。 今日も、そして明日も、同じ道を歩いて行く。 夢にたどり着くとは、そんなことでしかない。 考えてみれば、もともと地上に道などはなかった。 でも歩く人が多くなれば、そこが道になる。 夢にたどり着く道とは、そんなことで出来上がった道なのだ。 嵐のような逆風が吹いても、真正面から向かうしかない。 苦難や不合理の嵐もいずれ止むのだと信じて、明日もその道を歩いて行こう。
合宿
同志社大学在学中に体育会の空手部に無理やり引き込まれてから私の空手との関わりは 始まった。 極真の芦原道場が凄い人気だと聞いたのは二年生のころ。 三年生の時には 芦原道場の稽古が本当の空手だと思うようになっていた。 大学の剛柔流と極真は近いもの があったこともすんなり芦原道場に通うようになった理由の一つだった。 しかし、膝蹴りや肘打ちはまったく知らなかった。 顔面ガードをしながら肘のヘッドを 素早く回転させて相手のひたいを打ち抜く。 これは芦原道場ならではの練習方法だ。 実は、それを昨日の合宿で浜井代表がやってみせておられたので正直なところ驚いた。 私は極真の芦原道場、芦原会館京都支部、正道会館京都支部という経緯を経て、その後 再び極真東京城西支部で稽古を行うようになった。 しかし城西での肘打ち稽古は昔からの 型にはまった動作ばかりで初代芦原館長のような実践性はなかった。 言い換えれば 危ない空手を教えるのではなく試合に勝つための稽古が中心だったように思える。 昨日の合宿で浜井代表がやってみせられた肘打ちは、私が35年前に芦原館長から指導を 受けた肘打ちそのものだった。 しかし芦原会館でも正道会館でもない純粋に極真会館一本でやって来られた浜井代表が その打ち方を知っておられたとは。 そんな一つ一つの動作が新鮮でもあり驚きでもあった。 整列をする方向が右前からではなく左前からならぶこと。 これは浜井派の並び方なのだ。 城西でも芦原会館でも右前からであった。 そこは郷に入れば郷に従わねば。 そんなことを思いながら参加させて頂いていた合宿は4時間にも及んだ。 昨年は、土日を使い中国の本部道場まで一人で40人組手をしに出かけた。 55歳にして無謀だったかもしれない。 旅費、宿泊費、昇段料、昇段審査料全て合わせて18万円を使ってはみたものの 目標の40人組手を完遂することができず、30人が精一杯だった。 情けなかった。 そして身体が大きく荒々しい中国人を相手にそれが自分の限界だと思い知った。 その日があって、昨日の合宿がある。 感謝の気持ちとともに不思議なご縁を感じながら、昨日、昇段の賞状と帯を頂いた。 福井県から来られていた61歳の方は急性腎不全となってからも、週に3回の人工透析をしながら 極真空手の指導を続けられていた。 私は、あと4年でその方の年になる。 人工透析はそれをするだけで疲れるという。 もし自分がそうなったとしたらどうなるだろう。 透析を続ける身でありながら極真の稽古を変わらず続けられるだろうか? 腰の低い、物腰の柔らかい、その方を見ていると「心の強さ」とは、まさにこのような方の事を 言うのだろうと思われた。 あと何度、浜井代表を始め志を同じくする浜井派の先生方とお会いする事が出来るだろうか? 人の寿命には限りがある。 だから一回一回をより大事にしようと思いながら長野県戸倉からの帰路についた。
お遍路さん
元有名野球選手が四国でお遍路を黙々と歩いている。 人は常に変化の途上にある。 昇り調子があったかと思うと、あっけなく真っ逆さまに崖を転げ落ちたりする。 気を許すとこの様だ。 あまりの変化の大きさに心が付いていかない時だってある。 変化は修行という言葉に置き換えてもいい。 活きているとは、その修行の連続だ。 元野球選手の近況を読んでいて、そう感じた。 空手を教えていると、ふと思う事がある。 観て、真似して、覚えて欲しい。 集中して盗んで欲しい。 あえて教えない。 教えるのではなくやって魅せる。 スパーリングも移動も、型もすべてやって魅せる。 通信教育では、得られないコツの伝授がそこにある。 やって魅せねばならない。 すべては論より証拠だ。 良し悪しは直感で分かる。 いいものはいいし、良くないものは良くない。 だから今、この一瞬を見逃さないで欲しいと思う。 この感覚を盗んで欲しい。 全ては、その一瞬の中に凝縮されている。 今というその時を一生懸命に活きると、そこに行き着く事が出来る。 そのことに意味を見出して活きていくと、大事な一瞬に何度も出くわすことになる。 だからこそ努力する価値があるというものだ。 その努力があって初めて夢に向かう道筋も見えて来る。 その道なき道を時間をかけて歩いてみないか。 夢にたどり着くまで一緒に歩かないか。 夢は現実の中にこそ宿る。 今、荒れ果てたデコボコ道でも、自分自身の足で歩いて、そこに夢の種を埋めればいい。 自分の前に伸びる石ころだらけの道をただ黙々と歩む価値はそこにある。 太陽の威を借りて光る月よりも、小さくても自ら燃える蝋燭のように活きるには そうするより他に手はあるまい。
歯科医院
家の近くの交差点に5月中旬に歯科医院が出来る。 半年前にはそこから500メートル東に、そして1年ほど前には 家から歩いて1分の所に歯科医院が出来ていた。 なのにまた出来る。 歯医者さんはマーケティングという事をしないのだろうかと首をひねりたくなる。 それに5月に出来る場所は、角地だけど、今まで開業したお店は半年ともっていない。 最初は洒落た子供服のお店だった。その後別のショップ、それからオシャレな今風の 介護施設。それがいつの間にか閉じていた。 その後3ヶ月は入居者がなかった場所だから 近隣の人なら其処が商売に向いてない、いわく付き物件だとピンとくるはずだ。 なのに、そこに大きく「歯科医院 5月開業」という文字が現れた。 石を投げれば歯医者に当たる時代。 経営は難しかろうと察しがつく。 弁護士は司法試験に合格しても食べて行ける人は少ないと聞く。 それに法科大学院から司法試験に合格する割合は2006年に48.3%だったものが 2014年には22.6%にまで落ち込んでいる。 そんな合格率で世に出ても司法事務所に 就職出来ず公園で暇を潰す人は少なくない。 今年の歯科医師国家試験の合格率は63.8%だった。 しかし毎年の事だけど松本歯科大学とGReeeeNの奥羽大学を除けば70%は超える。 ただ歯学部の学費は国公立組であればまだいいが、私立では平均3000万円もかかる。 この先行投資には確実に回収出来る見込みがなければ進路を変える判断が真っ当だ。 そんなことを考えながら長津田駅北側の住宅街を歩いていたら 「歯科医院 5月19日開業」の文字が目に飛び込んで来た。 何で歯医者さんばかり増えるんだろう? やって行けるのかな? その歯科医院の立派な外観が気になってしようがない。 頭の良さとビジネスは別物なのに。 テストの点数は稼げてもお金を稼げるとは限らないのに。 運を引き寄せ、知恵を働かせる方法は学校では教えてくれないのに。 大丈夫なのかな? 来年のゴールデンウィーク、私の家の近くの交差点はどうなってるだろう。 たとえ高濃度ビタミンC点滴療法の内科であろうと eスポーツのお店であろうとも あの全戦全敗の場所では難しいかろう。 6月4日からの歯の衛生週間に向けて雨後のタケノコは、まだ芽を出しそうだ。 私にはわからない、生まれ死にゆく人は、どこからやってきてどこに去っていくのだろうか。また、生きている間の仮住まいを、誰のために心を悩まして、何のために目を喜ばせようとするのかということも、またわからない。家の主と家とが、無常を争っている様子は言うならば、アサガオとその葉についている露と同じようなものである。露が落ちて花が残ることがある。残るとは言っても朝日がさすころには枯れてしまうが。あるいは花がしぼんでも露が消えずに残っていることもある。消えないとは言っても夕方になるまで消えないとうことはない。 ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみに浮かぶうたかたは、かつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。 長明
ウォータースライダー
ダフネ、デュ、モーリアという方は1938年に31歳の若さで「レベッカ」を書き上げた。 その後「鳥」も書いた。 それをヒッチコックが映画にしてヒットさせた。 その91年前の1847年。31歳のシャーロット・ブロンテが「ジェーン・エア」を そして29歳のエミリー・ブロンテが有名な「嵐が丘」を世に出して翌年30歳で他界した。 不思議な事があるものだ。 共通することは30歳前後の若い女性であるということと文章力が並外れているということ。 そういうばアガサ・クリスティも1920年に30歳で作家デビューしている。 アガサは学校には行かず7歳まで字も書けなかったらしい。 それが30歳を過ぎると文字の達人になっている。 不思議な事があるものだ。 寂しく暗い幼少期は空想の世界で特有の能力を開花させ得るということなのだろうか。 話を元に戻そう。 ヒッチコックの「レベッカ」にはジョーン、フォンテーンという女優さんが出ている。 お姉さんは、「風と共に去りぬ」でメラニー役だったオリヴィア・デ・ハビランド。 2人とも東京生まれで、2人ともアカデミー主演女優賞を取っている。 兄弟姉妹で取ったのは、この2人しかいない。 不思議な事があるものだ。 妹は4回結婚し、姉は2回結婚している。 お父さんは96歳、お母さんは89歳、妹は96歳で亡くなった。 姉は99歳でまだ御存命だ。 これだけ波瀾万丈な人生なのに。 不思議な事があるものだ。 たとえば人生はロウソクのようなものなのかもしれない。 その灯が消えるまで自分では灯を消せないのではあるまいか? 何をやろうと、どれだけ苦労しようと、ロウソクの灯が消えるまで生きて行かねばならない。 もしそうだとしたら、他愛も無いことを気にしながらビクビク生きる人生なんて意味がない。 大地震が起こって多くの尊い命が奪われても、自分がいる部分に偶然、空洞が出来て 5日後に救出されることもある。 不思議な事があるものだ。 ただ分かっていることは大いなる流れの中で生かされている訳だからウォータースライダー のてっぺんに登ったら、あとは手を離して滑り落ちるだけのこと。 親切な人も、意地悪な人も、思い煩う人も、大胆な人も、みんな水しぶきを上げて滑り落ちる。 水の粒子に揉まれ流され落ちていく。 一粒一粒の圧力に負けるまで落ちていく。 天地が逆転して耳と鼻の奥に水と泡が届くまで落ちていく。 やがてその勢いも弱まって肩の力も抜けた頃、ようやくプールの底に辿り着く。 人生、摩訶不思議。 行き着く所まで行くようになっている。