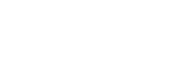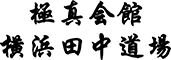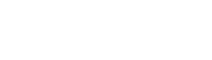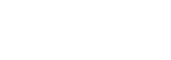試合
西田師範主宰の清武会第115回春季トーナメントに33人が出場させて頂いた。 結果としては入賞者は6名。(優勝1名、準優勝2名、4位3名) その他の方々も惜しい試合が多かったと思います。 空手は日常の稽古が大事。しかし非日常的な緊張感を経験することも大事。 そこに試合に出る価値がある。 スパーリングと試合は別物。鉛のように重く感じる手足と120%燃焼される心臓と肺。 相手の容赦ない蹴りとパンチ。この時ほど時計の針を意識することはない。 たった2分の必死の攻防がスローモーションのように感じられる。 「延長などしたくはない。」 でも判定で引き分け。 「あと2分もやるのか?」 2分という時間がこれほど長いと感じることはない。 「もういい、終わりたい。勝っても負けてもいい。」 そんな時に聞きなれた声が背中を押してくれる。先輩、後輩が応援してくれている。 「下がるな」、「前蹴り 入るよ」 「分かってるよ、でも足が上がらないんだ」 「頑張れ、残り30秒だ」 「まだ、30秒もあるの、無理だ。」 「ここからラッシュだ〜」 「相手の息づかいが聞こえる。相手は弱そうだったのに押してくる、あ〜無理だ」 お母さんの声、友達の必死の声援。
医学部 その17
3月18日に第109回医師国家試験の発表があった。 どこの大学も合格率を良く見せるために 毎年、各年次で留年を欠かさない。 但し東大、京大、阪大、九大など旧帝大はその必要はない。 合格率が低くても受験生は減らないのだ。 今年の京大は例年になく90%越を果たしたので頑張った方かもしれない。 ただ東大、京大の秀才もこれでは宝物の持ち腐れだ。 いくらいいものであっても放ったらかしで磨かなければ只の石になってしまう。 群馬と富山の合格人数は巷の噂に反して、以外に悪くない。 中には、やはい純粋に努力を積み重ねて来ている学生がいるということなのだろう。 私立の医大は合格率を維持しなければならない。 「偏差値上げ」と「受験者数増加」が命題なのだ。 しかし獨協、埼玉、杏林、東京女子、東海、北里は毎年合格率は低い。 これらの大学に共通していることは比較的留年は少ないということ。 この方針も悪くはない。 独特というか、開き直っているのは帝京だ。 毎年、大量の学生が国試を受け、大量の学生が落ちて合格率最下位近辺を維持している。 留年はもちろん多いし、卒業までの学費は5000万円~6000万円は下らないと云う。 開業医の子供で、少々勉強が苦手なお子様が通う医大なのだ。 ーーーーーーーーーー出願 受験 合格 合格率ーーーー 北海道大学医学部
医学部 その16
去年の3月14日に同じようなブログを書いていた。 「医学部 その15」 悩みもなく、睡眠不足もなく、苦労もない。 そんな人生などあるのだろうか? 汗まみれで、精一杯で、眠りに落ちたと思ったら朝を迎える。 それが人生だと思って生きて来た。 際限もなく続く暗闇のただ一点の仄かな明かりを頼りに生きる。 それが人生だと思って生きて来た。 だから、豊かで、楽しく、安心して、長生きができる人生が羨ましい。 それが正直な気持ちだ。 でも、実際に、そんな時を過ごすようになると、きっと、その怠惰な時を持て余してしまうだろう。 苦労があって、ハラハラドキドキがあるから、人生なのだ。 それが私の魂の喜びだ。 一昨日、長男からメールが来た。 「進級出来たよ」 簡単な、素っ気ないメールだった。 でも、そのメールで私は暫しの安堵を得ることが出来た。 この4月から医学部6年生になる。 あと1年か。 ふとそう思った。 もう、このハラハラドキドキもあと1年で終わってしまう。 何だか、微妙な気持ちが湧いてきた。 子供が独り立ちする時は、もう遠くはないのだ。 find a date in american historycs go matchmaking ranks system 子供が自分を超えて行ってくれる嬉しさと、そして僅かな、もの寂しさが入り混じる。
今日を生きる
夢を見た。 大学に行ってるけれども、授業に一度も出ずに期末を迎えようとしているらしい。 click heredating your ex girlfriend's sistervisit website 流石に焦った。 というか焦るのが遅すぎる。 何でゼミで馴染みの人に試験の予測くらい聞いて おかなかったんだろう? そういえばここ数カ月朝から授業に出た覚えもない。 さあ、どうしよう。 どうして、こうなったんだろう。 何でバイトにばかり気が向いて勉強のことはほったらかしにして しまったんだろう。 すべては後の祭りだ。 流石に困った。 打つ手なし。 ハッとして目が覚めた。 そこにはベッドに寝てる中年のオヤジがいるだけだった。 あ~良かった大学生じゃなかったんだ。 胸をなでおろしているオヤジがいた。 テレビが点けっぱなしだった。 寝る前に長男の進級のことが気になっていたんだった。 そういえば医師国家試験の結果と6年生への進級の結果がそろそろ出るころなのだ。 例年3月17日前後にそれは分かる。 医師国家試験は来年の110回が本番だ。 それを今から気にしている親がいる。 長男には決して聞かないし顔にも出したくはない。 でも本音は医学部受験を意識し出して、かれこれ16年の総決算なのだ。 親も陰ながら応援もし、意識もしている。 でも今日はあれやこれやと考えながらテレビを点けたままうたた寝をしてしまった。
変化
スタンリー・ジョーダン三昧の日が続いている。 天国への階段、イエスタデイ、オーバーザレインボウ タッピングについては賛否両論あるけど、やっぱり凄い。 左でリズムを刻んで、もう一台は右手でリードするなんて見たことない。 彼の演奏を観てると、口を開けて間抜けな顔で見惚れてしまっている自分に出くわしてしまう。 三寒四温は桜が咲くまで続く。 そして花粉もまだ続く。 しかし、おおよそこの世の中には不変のものは一つもない。あと少しの辛抱だ。 お互い平穏な日々が続くと、ともすると今の平穏な日々がこの先も永遠に続くのではと錯覚してしまう。 それは人間である以上しようがない。 しかし我々は常に危険や変動、変化と背中合わせに あることは忘れてはならない。 長い目で見ると大変な変化が起こっている。 昭和16年の小学校教員の初任給は50円だった。それが7年間で(昭和23年)2000円に。 9年後(昭和32年)には8000円だ。今は200000万円前後ではないだろうか。 74年間で4000倍になっている。 我々は、常に変化の中にいる。 だから、その変化に鈍感になってしまうのかもしれない。 72年前の東京で理髪店に行くと大人は、0.8円だった。 しかし、そのことは日本人の脳裏からは 消えてしまっている。 それはもっともなことだ。
棘
人には、未知なることがたくさんある。 子供にとっては世界は未知なる宝庫だ。 だから子供達の目は輝いている。 そして自然は刻々と変化し進化する。 歯が生えて、背が伸び、体重が増え、やがて背中が曲り、痩せ衰えて灰になる。 http://www.fatihmatbaa.com/qx/radiocarbon-dating-worksheet/personal assistant jobs readingonline dating how to tell if a guy is interestedhow often should you talk to the person you're dating 変化する可能性が山ほどある子供達は毎日が希望に溢れている。 女性が母になり、子供を身ごもると願い事が一つ増える。 ただ、お腹の子供が無事に、そして元気に生まれてきて欲しい。 その一念だ。 それが願いであり、それが祈り。そしてそれが希望というものではないだろうか。 心に「希望」を持って生きよう。 この母が子を思う純粋な願いや希望の心には邪念がない。
おざなり
浜井代表とKさんと三人集まればいつも楽しい飲み会になる。 south african dating customschristian dating site hong kong 私はこの雰囲気が好きで、先週に続いての飲み会になった。 そんな楽しい飲み会で気分の悪いことが話題になった。 YouTubeの女子プロレスの試合を観てから気分がすぐれない。 まさにそのことだ。 格闘技をやったことがある人なら分かるはず。 体重差があっての馬乗りパンチはプロレスでは見たことがない。 それをやりたいなら、女子総合格闘技MMAか、日本ならjewelsでやればいい。 それを「魅せるためのプロレス」でやってはならないし、弱い人間が禁じ手を使って 勝ち誇った姿を観るのが腹立たしい。 世の中では体重差があっても、気にせず、軽い相手をやり込める人間がまだいるようだ。 川崎の中学生が殺されたというニュースを何度も見た後だけに、抑えきれない憤りを感じている。 イジメがあるという。 それは当たり前だ。 そんなことは今に始まったことじゃない。 ではどうすればいいのか? 簡単なことだ。 いじめられない、いじめの標的にならないことだ。 いくらいじめをやめなさいと言ったところで、なくなりはしない。 そんな綺麗ごとで済むものではない。 なら、いじめられないようにするしかい。 私はそんなことを思いながら子供達の稽古をしている。
体幹トレーニング
今日は飲み会のつもりで行った本部道場で何故だか稽古をする羽目に。 ところが今日の東京本部道場の稽古は体幹トレーニングがメイン。 いつもと違うなあ、と思いながら準備運動、そして息が上がるスクワットなどの クイックトレーニング。その後に体幹トレーニングは意外と効きました。 スパーリングで圧されない体幹を作る。 これは大事かもしれない。 いくらベンチプレスを130kg上げてもブレてはダメだ。 今でも私は、夜のトレーニングで筋トレを少なくても1時間以上、週に3回はやる。 でも、体幹とは違うものだと分かりました。 一流のサッカー選手の動きの裏には、この体幹トレーニングがあったのか。 これは、空手の稽古にも応用してみようと思う。 東京の夜に、仕事を終えて集まる同士がここにはいる。 大山総裁に感謝。 そして浜井代表に感謝の一言です。
東尋坊
人を倒すことなど簡単にできることではない。 稽古を終えるといつもそう思う。 スパーリングをやれば、すぐに息が切れて足や腕が鉛のようになってしまう自分に 出くわしてしまう。 いくら走っても、いくら稽古をしても、そう簡単に上達はしない。 でも身体は正直なもので、そうやって、地味な努力を受け容れてくれている。 ただ一つ一つの細胞にその変化を伝えるのに時間が少々かかるだけなのだ。 北風が窓を鳴らす明け方、疲れた身体を休めながら布団の中で耳を澄ませる。 風の向こうに新聞屋さんのバイクの音を聞いた。 ウトウトしながら長い間思い出す事のなかった遠い昔のことを思い出した。 これまでに交わった人達の温もりが蘇って、自分は一人ではなかったと気付いた。 北風の凍てつく寒さの中で心にほのかな灯が点された。 身体の自由が利くのであれば、その自由を思う存分使い切るがいい。 身体の自由が利かないのであれば、心の自由を思う存分使い切るがいい。 今、出来る事を思う存分試してみる。 そんな生き方をしてみよう。 そんなことを思いながら静かな朝を迎えた。 駅に向かう道で行き交う人々。 勤勉で真面目な人ほど人に迷惑を掛けたくはないと思っているのかな。 勤勉で真面目な人ほど「助けてください」とは声に出せないのではないだろうか。 でも手を貸したがっている人や、役に立ちたがっている人は少なくないかもしれない。 「あなたでも役に立ちますよ」と誰かが囁いた気がした。 今をギリギリのところで生きている人がいる。 張り詰めた心の人がいる。 そんな人に「今」を贈りたい。 きっとあなたを思う人が居て、「今、採ってきたよ」と果実を分けてくれる人がいる。 凍てつく寒さはまだ続いている。 背中は丸くなる。 そして歩きながら思った。 人はきっと機会があれば役に立ちたがっているのではなかろうかと。 そう思うと何だか今日も満更じゃなさそうな気になってきた。
ジェラルディン・マクイーワン
ミス・マープルの女優は何度か代わっている。 アガサクリスティーのドラマが好きだ。 英国の推理、ミステリーが面白い。 シャーロックホームズも何とも言えない面白さがある。 2015年1月30日 82歳で味のあるミスマープルさんが旅立っていた。 知らなかった。 岸田今日子さんの吹き替えもいい。 味があった。 その女優さんが急に居なくなってしまった。 みんな、その日をいつかは迎える。 でも突然すぎる。 忙しい時にその日は来る。 えっ、その日は予定が、、、っていう時に突然訪れる。 でも、私は必ず行く。 お別れをしなければ気が済まないからその人に別れを言いに行く。 そんな日は重なるものだ。 でも行く。 別れを言わねば、、、。 急に人は居なくなる。 姿を見せなくなる。 それも忽然と、、、。 人は必ず旅立っていく。 万物は日々生成発展している。 病も老いも、そして死さえも生成発展の姿なのだ。 子供が好きで、子供が欲しくて、「おめでたです」と言われ やっと授かった赤子が一月もせず旅立つこともある。 来る日も来る日も仕事は手につかず、ただ祈る日を過ごして、やがてその日を迎える。 家では、色とりどりのものが赤子のためにと色どられている。 妻は、そんな家に帰らねばならない。 でも人間は忘れる力を持ち合わせている。 そんな時にはそれに掛けるしかない。 人には思い出したくないことが一つや二つはあるものだ。 しかし、そんな落ち込んでいる人を思い、その部屋の色とりどりの赤子のベッドやおもちゃを かたずけてくれた人がいることを忘れてはならない。 どんなに辛く、涙ながらに、その可愛い、いたいけなその子供服を袋に詰め どんなにか楽しい日々が待ち受けていることかとワクワクしながら買ったおもちゃも 決して見せる訳にはいかない。 捨てないとならない。 妻には見せることは出来ない。 心を閉ざした妻を思うと全てを元に戻さないといけないと思って仕事どころではない夫もいる。 そしてみな、心に住み着いた悪魔を忘れようと生きて行く。 この世に神様は居ない。 そう思う時もあっていい。 でも、あなたを思い、あなたを気遣い、あなたの心に少しでも安らぎを与えようとする人がいることは 忘れてはいけない。 あなたが苦しみを味わい、いつの日かそれを話せる日が来る日まで、きっと その人はそばにいてくれるはずだから。 言葉ほど頼りないものはないのに、人は言葉によってしか、お互いの心を確かめられずにいる。 私の心は震えている。 でも、もっと震えている人を何とかしたい。 まだ私は生きている。 だから言葉で伝えて行こうと思う。 あなたをいつまでも思っていると。